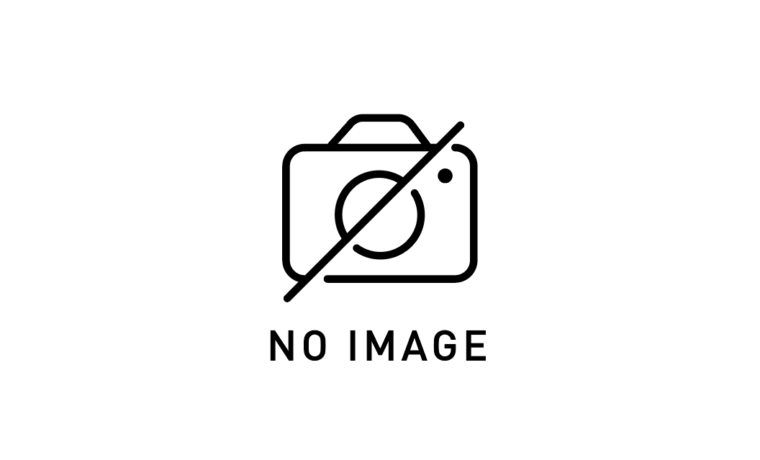どうも、武器商人です。
僕はダーツブログをはじめて8年ほどになりますが、ダーツバーよりも漫画喫茶で投げることが多かったです。
今ダーツプロとして活躍している選手を見ると、ダーツバーでダーツをはじめた人がとても多いです。たまたま行ったバーにダーツが置いてあって、投げてみたら面白かった。負けたのが悔しくてのめり込んだ。
そんな“王道のキッカケ”をよく耳にします。
でもその一方で、「漫画喫茶でダーツをはじめた」という人も意外と多くなっている。そして、そういう層からプロになり、今まさに活躍し始めている選手も増えてきています。
Xのタイムラインなどでは
「漫画喫茶でダーツをしている人はマナーを知らない」
といった意見を見かけることもありますが、僕は少し違う考えを持っています。
ちょっとした文化の対立みたいな構造が起こっているので本記事を書いてみようと思いました。
『孤独のボウリング』が言う社会関係資本
ダーツって、スポーツという観点でいうとビリヤードやボウリングなどと似たところがあるんですよね。
ソフトダーツブームより少し前に起こったボウリングブームには、参考になりそうな書籍があります。
『孤独なボウリング』は、アメリカ社会で社会関係資本(人々のつながり)が減少し、コミュニティが崩壊していると論じる本です。
ボウリングの参加者そのものは減っていないのに、社交としてのボウリング――つまり「誰かと一緒に投げる」という文化が激減している点に着目し、社会から“つながり”が失われつつある現状を指摘しています。
これって、最近のダーツにも言えることなんじゃないかと、僕はかなり興味深く観察しています。
ダーツに限りませんが、世の中に「1人〇〇」や「ぼっち〇〇」という言葉が増えている背景には、まさにこうした社会関係資本の低下があると思います。
ボンディング(内部のつながり)/ブリッジング(外部つながり)
ボンディング・・・内輪の強い結束
ブリッジング・・・異質な集団を繋ぐ架け橋
社会を健全にするのはブリッジング資本であり、ボンディングだけではコミュニティは閉鎖的になり、やがて衰退すると言われています。
ダーツ業界でいうと、「昔ながらのダーツ界」はまさにボンディングそのものです。
ダーツができる場所といえばダーツバーで、PERFECT/JAPANの選手もバーを拠点に活動している人が多い。スポンサーにもバー文化で育った選手が多く、強い結束があります。これは健全な“内輪の力”ですが、同時に外から入りづらい構造でもあります。
一方で最近は、ダーツライブホームなどの家投げ環境や、漫画喫茶からダーツを始める層が増えています。
Xでは「漫画喫茶でダーツする人はマナーが悪い」といった意見も見かけますが、僕はそれを“文化の成り立ちの違い”だと考えています。
昔、ゲームセンター全盛期がありましたが、家庭用ゲーム機の登場でプレイ場所が家へ移りました。
だからといって「家庭用ゲーム機勢はマナーが低い」とは誰も言いませんよね。単に“場所が違えば文化も違う”というだけの話です。
ダーツも同じで、ダーツバーは“お酒を飲む場”なので厳しいマナーが必要です。
対して漫画喫茶にはその前提がないため、漫画を読みながら台を占有する人がいたり、学生グループが騒ぎながら投げることもある。ダーツバー文化で育った人からは異質に見えますが、漫画喫茶では自然な行動でもあります。
ここが重要で、漫画喫茶はまさに“ブリッジングが起こる場所”なんです。
異質な集団が混ざることで新しくダーツに触れる人が増え、閉じたコミュニティが外側とつながる。これこそが社会関係資本におけるブリッジングの役割です。
だから、多少の文化の衝突は“健全な成長のプロセス”だと僕は思っています。
みんな仲良くしましょう!
大事なことなので、もう一度言います。
社会を健全にするのはブリッジング資本であり、ボンディングだけでは閉鎖的になり衰退する。
漫画喫茶は現代の“第三の場所(サードプレイス)”
サードプレイスとは、家(第一の場所)や職場(第二の場所)ではない、人がゆるく集まれる“第三の居場所”のことです。『孤独なボウリング』では、このサードプレイスの消失が社会関係資本の低下を招き、人々の孤立につながったと指摘されています。
ダーツで言えば、
・漫画喫茶
・カラオケ
・アミューズメント施設
など、誰でも気軽に立ち寄れる場所がサードプレイスにあたります。
ダーツバーはどちらかというと“職場寄り”で、第二の場所に近いと感じています。
こうしたサードプレイスでは、「たまたま居合わせた人」や「少し話す程度の相手」といった弱いつながり(Weak Ties)が生まれます。社会学では、この弱いつながりこそがコミュニティの入口となり、人の孤立を防ぐ“社会の潤滑油”だとされています。
実際、ダーツ業界でも漫画喫茶や家投げといったバー文化とは異なる場所からダーツに触れる人が増えています。これはサードプレイスのブリッジング機能が働いている証拠で、コミュニティを開いていくために欠かせない存在だと思います。
僕自身も、X(旧Twitter)のスペースで夜な夜な配信しながら、全国のさまざまな人と交流しています。地域も年齢も性別も違うし、ホームショップやリーグのしがらみもない。まさに“弱いつながり”でゆるく結ばれたコミュニティです。なので、僕のやっているスペースはサードプレイスと呼んでも良いかもしれない。それがすごく楽しいんですよね。もしこのつながりがなければ、僕はダーツを続けていなかったかもしれません。
漫画喫茶はなぜ“ブリッジングの中心地”なのか?
漫画喫茶はなぜ“ブリッジングの中心地”なのか?
・誰でも入れる
・料金が安い
・深夜でも投げられる
・人目が気になりにくい
・初心者の心理的負担がほぼゼロ
・ダーツバーとは人種が違う
ダーツバーはどうしても敷居が高いですが、漫画喫茶は初心者でも気軽に入れる“入り口”として機能しています。こうした場所は業界にとってとても大事です。
この入口が有るのと無いのとではダーツ人口の増加は全然変わってくると思いますよ。
「漫画喫茶でダーツを始めた人はマナーが…」問題への回答
確かに、漫画喫茶でのダーツはダーツバーより少しカオスになることがあります。
ただ、これは 文化の成り立ちが違うだけ で、もともと別のコミュニティなんですよね。価値観が違えば摩擦が起きるのは当然です。
漫画喫茶がダーツ業界を支えるようになっていきている
漫画喫茶は、すでにダーツ業界の内側に食い込み、大事なポジションを占めています。
漫画喫茶スタートのプロプレイヤーもいますし、普段ダーツバーで練習している人でも漫画喫茶で投げることは珍しくありません。
さらに、自遊空間はPERFECTのメインスポンサー、快活CLUBはJAPANトッププロの有原竜太プロをサポートするなど、漫画喫茶はすでに ダーツ界と密接に結びついた存在 となっています。
まとめ
漫画喫茶でのダーツは、ただの“初心者向けの遊び場”ではありません。家でも職場でもない第三の場所として機能し、新しい人がダーツに触れるための重要な入口になっています。
ダーツバーのようなボンディングだけではコミュニティは閉じてしまいますが、漫画喫茶のようなブリッジングの場があることで、外から人が入ってきます。多少カオスでも、それが正常なんですよね。
ダーツ人口が増えるためには、こうしたサードプレイスの存在が欠かせません。
入口が多いほど、ダーツの文化は強く、太く育っていくと僕は考えています。
そして最後に……
僕自身も、これからはもっと漫画喫茶に行って、たくさん漫画を読もうと思います。
――いや、そっちか(笑)
おすすめの漫画があればぜひ教えて下さい!